ホーム > 四国中央市で雨漏りによる屋根板腐朽!板交換のために淡路いぶし…

四国中央市で雨漏りによる屋根板腐朽!板交換のために淡路いぶし瓦の取り除け復旧を実施
四国中央市 屋根材(瓦)
【工事のきっかけ】
四国中央市でお世話になっている大工さんから「雨漏りしている家がある。屋根板や垂木も腐っているから見に来てほしい。」と依頼がありました。現場確認に行くと屋根は庇のような下屋根で棟の中に樋が通っていました。樋部分中心に屋根板等が腐っており危険な状態でした。樋の寄せマスが棟に埋まっていることと樋部分の淡路いぶし瓦部分のみ土がゴッソリ流れていました。
樋の配置と屋根板を交換しないと状態がひどくなる一方でしたので、樋、屋根板工事による瓦の部分撤去、復旧を実施しました。
基本情報
- 施工内容:屋根材(瓦)
- 施工期間:撤去1日、復旧1日(瓦のみ)
- 使用材料:淡路いぶし80判、ゴムアスルーフィング、シルガード

みなさんこんにちは。街の屋根やさん新居浜中央店の合田です。
本日は風が非常に強いです。2年前は物凄い春の嵐で瓦トラブルがたくさんありました。
このような風の強い日は屋根を気にされる方も多いかもしれません。
台風ではないですが、新居浜市、四国中央市のみなさまはやまじ風にも気を付けましょう。
何か気になることかあればお気軽にご相談ください。
関連ページ
早めに台風対策!被害を抑える屋根とお住まいのチェックポイント
今回は四国中央市土居町の現場です。雨漏りが原因で垂木や柱木までが腐ってしまった現場です。
大屋根からの雨漏りではなく下屋根からのようです。
どうやら大屋根部分から伸びている2本の樋が棟の中を通っていてその付近のみ漏れているようです。
屋根板の様子です。樋がある所を中心にかなり雨漏り後が広がっています。
垂木や柱木は誰が見ても腐って、屋根が落ちまいか心配になるほどです。
大工さんの支え木が活躍しています。
雨漏りを放置すると知らず知らず広範囲の修繕が必要になります。
雨漏りは発生して初めて気づくパターンが多いので気が付いたら早めの対応をしましょう。
庭の通路部分のみ棟を積んでいますが樋が棟に入っています。
空洞部分もあり雨が直接入るリスクもありますが、大屋根の軒の出もかなりあるので
雨が直接入る量は多くは無いはずです。
しかし木を腐らす程の雨漏りです。おそらく樋に何かしらトラブルがありそうです。
樋周りを漆喰で防ぐのは意味が無さそう・・・
屋根下の竪樋が1本だけ伸びていていることから棟の中で2本の樋を1本に集めていると予測できます。
瓦の隙間から覗くと、棟の土もかなりスカスカ状態です。
2本の樋を1本に集約する時に使う寄せマスという部材が棟の中にあると思います。
現時点では、
・棟の中での樋そのもの破損
・寄せマスから雨水があふれているか
が考えられます。
棟の中の土も
・乾いてパラパラになり寄せマスの詰まる原因になっているのか
・寄せマスからあふれた雨水のせいで土が流れているか
色々予測は建てられます。
蛇の抜け殻がありました。可能性は低いですがべビが詰まりの原因とか・・・それは無いかな(笑)

寄せマスは先述通り、2本の樋を1本に集約する部材です。
主に屋根では寄棟屋根に見られます。寄棟屋根は全てが軒先になるので
ぐるりと樋が囲んであります。
ただし全箇所に縦樋を付けると外観が損なわれるので、竪樋の落す集水器が近い
場合はこの寄せマスで1本に集約しています。
もちろん2か所分の雨水を集めるのでかなりの量の雨水が1か所に集まります
枯葉とかがここで詰まったりするとかなり寄せマスから雨水があふれるので定期的な掃除
が必要です。
雨漏り箇所の瓦を剥いでみました。
下は土葺きでしたが、部分的に土が全て流れています。その部分はやはり樋の部分。
樋からあふれた雨水が瓦下の屋根板に直接流れている状態は間違いないみたいです。
最後に取り除けた瓦の寸法を測っておきました。
標準より小さかったので、使えない瓦があった場合取り寄せに時間がかかる可能性があるからです。
瓦にはサイズとそれに伴う効き幅というものがあります。
効き幅は簡単に言うと瓦1枚で屋根を覆ってくれる寸法です。上下左右に重なっている部分は含みません。
葺いてある瓦は赤矢印の寸法で計測します。矢印外の土が付いている部分は重なっているので含みません。
和型瓦の左上と右下の欠いである部分をカギと言います。瓦葺をすると葺く瓦の左上と右下の瓦のカギと合致します。
また瓦を正面から見て棟側の上の瓦に被る部分を水上、軒側を水下と言います。
葺いていない瓦の寸法の測り方は様々ですが、カギに引っかけて測る場合は末端から引っかけてない方のカギの長さを引きます。
右写真では水上のカギに引っかけているので末端までの長さから水下分の長さを引きます。
分で説明は難しいですね。
横の効き幅は215㎜前後 流れの効き幅は215㎜位の水下のカギが30㎜程なので185㎜前後でした。
瓦の大きさで規定寸法は定まっています。ただし会社ごとに微妙に違ったり、自然のもので作っているので
実際に焼きあがった時に若干異なることもあります。
今回は淡路いぶし80枚判が一番近いです。
80というのは屋根面積1坪(3.3㎡)葺くのに必要な瓦の枚数を表示しています。
標準は1坪53枚で葺く53枚判です。菊間は64枚判か72枚判です。
他にも56枚判、58枚判、60枚判などあり地域によっても大きさが変わったりします。
数字が大きくなるほど瓦は小さくなります。

一通り調査は終了です。
現時点では樋が原因の可能性が高いですが、屋根板や垂木を変えざるを得ない状態なので
その部分の棟と地伏せの撤去及び復旧のお見積りをいたしました。
雨漏り箇所は樋部分ですが、屋根板の腐りが広がっていたので取り除け範囲もその分広がります。

まずは養生です。
現場調査と打ち合わせ時に
・屋根には土が入っている。
・瓦撤去→板や柱木、垂木の交換→瓦復旧
等、状況や工程を予め決めているので工程に合った作業準備を
行います。
ブルーシートを屋根下と少し離れた隅の方に2か所敷きます。
作業中はどうしても土が落ちてしまいます。土はシート内でまとまるので片付け
の時短になります。
隅の方に敷いたシートは取り除けた瓦の保管場所です。
今回は解体ではなく復旧なので除けた瓦はまた使用します。
本来は近くに置く方が時短ですが、後日大工さんの作業が入るので邪魔にならないよう配慮です。
板金屋さんの樋の撤去も同日でした。棟の中に樋が通っているので瓦撤去作業は少し待って
樋カットの作業を先に実施しました。雨漏りの原因は樋の可能性が高いので私もどうなっているか
気になっていました。
埋め込まれているたて樋の10㎝上をカットすると土がこんもり体積しています。水を吸いすぎたり
様々な要因があると思いますが真っ黒です。
寄せマスを使用している樋なのでかなりの水がこのたて樋を流れます。
この土のせいで雨水が樋の中で溜まり水かさが上がり棟の中の寄せマスであふれたのだと思います。
土をかき出してホースで水を出しながら土を抉り出すも中々取れません。
さらに途中でつっかえてどちらに樋が通っているのか分かりません。
しかも中の土が崩れるのか、ホースの水が通ったり詰まったりも繰り返します。
高圧洗浄機でさらに土を抉りだして見ました。通りは良くなりましたが
この樋がまだ使用出来るかどうかは分かりません。どこで排水しているのかも不明です。
そんな時、うちの職人が気付きました。
実はこの屋根がある場所は家の中庭なのですが、土に埋まった亀坪や石材のモニュメント、
もしかするとこの場所は元々池があったのではないかと。
家の方に尋ねるとアタリです。40年程前には池があったと言うことでした。
今は大量の土で池は無くなっています。
もしこの樋の土が池を埋めた時に破損や塞がれたとしたら・・・
結論ここの排出口は塞ぐことになりました。
屋根の撤去を行います。
今回は下屋根の狭い空間です。脚立で作業を行います。
棟の取り除けは屋根に乗らないと出来ません。
屋根板が腐っているので上る人間は1人のみです。
一番上の紐丸瓦から取り除け、次の紐のし瓦までに乗っている土を取り除けます。
棟瓦の撤去は、上から瓦→土→瓦→土の順で取り除けます。段数が多いほど作業は
多くなります。
他の職人は取り除けた瓦の清掃です。
昔は大量の土でしっかり押し固めて施工しているので除けた瓦側にも土が
くっついています。
復旧段階で除けるのではなく、取り除け段階で清掃する方が、残土処分作業も減り
復旧作業もスムーズにいきます。
取り除けた瓦は先程隅の方に敷いたシートの上で保管です。
あまり使われない小さいサイズの瓦なので予想外の破損などあると追加注文が必要に
なります。常時置いてあるサイズではないのですぐに手に入らないのが辛い(´;ω;`)
途中経過です。だいぶ取り除けが進んでいます。早い。
屋根板の取り換えはこの面のみなので、棟はこの面側部分のみ撤去した時点で
大工さんに板替え出来るかどうか確認してもらいました。
あとは葺止め部分です。葺止は壁際部分のことです。壁際まで瓦を葺いたら、
雨が壁伝いに家に入り込まないよう雨押えという板金を壁の中に埋めた状態で壁際の
瓦を多い被せています。
もちろん壁際にも大量の土が入っています。
取り除けが終わりました。
大工さんの板貼り替えに必要な範囲も十分取れています。
後は屋根上の土を取り除ける作業です。
取り除け後の写真は撮れていませんでした。すいません。

最後にブルーシート養生です。
板を貼り替えるので防水シートは貼れませんのでシート養生のみとなります。
たてに伸びているビニールは取り除けたたて樋の応急ビニールです。
軒樋は残っているので雨がふるとビニールをしていない場合、雨がたて樋に落ちる場所から
バシャバシャ落ちるので樋の復旧までの応急処置です。
すいません。前回土の撤去後の写真が無かったと言いましたがありました。
水が屋根板に浸透しているのがすぐ分かるくらい黒ずんでます。
板の交換により綺麗な屋根板に変わっていました。
雨漏りを放っておくと屋根板がこんなに傷みます。板が腐っていくと
瓦の重さに耐えられなくなり屋根が沈んでしまいます。
昔の土葺き瓦屋根は現在の桟打ち瓦屋根の2倍は重いのでもちろん、桟打ちの
瓦屋根も屋根板が腐ると釘の効き目も弱くなります。
軽い屋根材ももちろん同様です。軽いとは言え釘やビスが効かないと、台風などの
被害に会いやすくなります。特に金属屋根は釘やビスの長さが短いので屋根板の状態
は重要です。
瓦が重いのが最大要因ではありません。土台が弱くなっているのが重要です。
最初に防水シートを貼ります。ゴムアスルーフィングを使用しました。
防水シートは雨漏りを防ぐ最終手段です。屋根材から雨が侵入しても防水シートが
雨漏りから守ってくれます。
平面はもちろん、壁際もしっかり立ち上げで吹き込みでも防水シートに流れるように
します。
次に瓦の桟木を打ちます。
淡路瓦の流れ寸法を測って瓦の引っ掛け部分に桟木を横に真っすぐ打ちます。
普段は防腐処理した幅30㎜、厚み15㎜の桟木を打ちますが、今回は80判の小さい
瓦で土葺きだったので、普段の桟木は逆に高くなりました。
厚さ3㎜くらいの木ずりを4枚重ねて桟木変わりにして対処しました。
桟木に打つ釘は垂木の上に打ちます。垂木上に打つ理由は
・屋根板から釘が見えないようにする。
・桟木をしっかり効かす。
などです。
漆喰の準備です。
街の屋根屋さん新居浜中央店は瓦用漆喰「シルガード」を使用します。
今回は外壁が左官で白く塗っているため白色を使用します。
シルガードは水を弾く役割が大きいので、現在は棟や葺止(壁際)など土を積む部分の
土の代わりに使用しています。
また今回のように土葺きの部分復旧の時は、桟打ち部分と土葺部分では高さが
結構変わるのでシルガードで高さ調整を行います。
地伏せ復旧開始です。
先述通り漆喰で高さ調整をしながら復旧します。
淡路いぶし瓦のような和型は下から上へ、左から右へ施工します。
初めの高さ調節が重要です。ここがズレでしまうと復旧した後
全体的にみると右に行くにつれ段々低くなってしまいます。

地伏せ復旧も完了間近です。
最上段までシルガードで高さを合わせていきます。
屋根上の低姿勢作業は大変です。
地伏せが終わると次は棟と葺止めです。
この屋根は桁葺止と棟、昇り葺止めが連続しているので
のし瓦の高さをそろえていきます。
糸で高さをそろえて、土の代わりに漆喰を敷き詰め面戸瓦、のしを
積んでいきます。
シルガードを詰めてのし瓦を積む、またシルガードを積んでのし瓦を積む。
を繰り返します。
ここは棟の2段目と3段目に松皮菱のしを積んでいました。
今は中々見ないですね。飾りのついた棟瓦を見ると立派なご自宅だと
この仕事を通じて思うようになりました。
のし瓦もだんだん積みあがってきました。
葺止は5段積みなのでこれで終わりです。
最後に紐丸雁振を取り付けます。
紐丸には銅線が通る穴があって、銅線を括って固定します。
銅線は屋根板に釘を巻き付けて固定するため、一番下の屋根板と一番上の雁振が
連結する形になります。
今回は棟を板替えする半分のみ取り除けたので既存仕様での復旧でしたが、
現在は強力棟工法が定まっています。
強力棟とは地震や台風で棟が崩れにくくするための工法です。具体的には
・左右の、のし瓦同士を銅線やステン線で連結して互いを引き合わせる。
・雁振は銅線ではなくビスで固定する。
・雁振をビス固定するために棟木と棟金具を使用し屋根板との連結を強化する。
作業や材料は増えますが天災の被害に合わないようにするために瓦も基準が変わっています。
現在では新築や葺替えする場合はこの工法が必須です。
壁との取り合いはモルタルで固めていたのでシルガードで
同様に仕舞をつけました。
一先ず復旧が終わりました。
最後に掃除をして作業終了です。
土の塊だけでなく釘や銅線も落ちやすいので
よく確認を心がけています。
。
板も綺麗になり屋根瓦も復旧できました。
いつ崩れてもおかしくなかったのですがお客様も安心です。
樋復旧が残っていますが今回の私たちの作業は無事終了です。

最後までご愛読ありがとうございました。
今回のように樋が棟の中にあり、そこからあふれた雨水によって
雨漏りするなど、かなり珍しいケースでした。
ですが、雨漏りを放っておくと内部被害がどんどん拡大していくことは
今回の事例は分かりやすいケースでした。
雨漏りが分かればひどくなる前の解決を!
四国中央市で屋根でお困りの事があれば街の屋根やさん新居浜中央店に
お気軽にご連絡ください。
その他の地域の方も大歓迎です。
街の屋根やさん新居浜中央店
0120-32-6886
ご相談、お見積り、点検は無料です。
屋根工事のご依頼・ご相談が初めての方
この記事を書いた加盟店

電話 0120-989-742
E-Mail machiyane-niihama@higaki-roofest.com
桧垣スレート株式会社
〒792-0811
愛媛県新居浜市庄内町3丁目1−46
愛媛県の加盟店一覧

電話 0120-989-742
E-Mail machiyane-ehime@tankawara.co.jp
有限会社丹瓦建材店
〒793-0073
愛媛県西条市氷見丙466

電話 0120-989-742
E-Mail machiyane-ehime@tankawara.co.jp
有限会社丹瓦建材店
〒791-1102
愛媛県松山市来住町798−7
ベルメゾン南久米102号室

共通の施工事例はこちら
記事がありません
表示する記事はありませんでした。
各種屋根工事メニュー
私たち『街の屋根やさん』は神奈川県を含む関東全域を施工エリアとする、お住まいの屋根の専門店です!
街の屋根やさんでは下記の工事を取り扱っております。工事内容の詳細は各工事ページでご確認下さい。

街の屋根やさんが施工している様々な屋根工事と屋根リフォームの一覧をご紹介します。

お客様の不安を解消できるように、お問い合わせから工事の完成までの流れをご紹介しています。

街の屋根やさんが施工している様々な屋根工事と屋根リフォームの一覧をご紹介します。
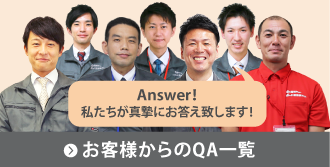
お客様から寄せられた屋根に関する疑問を、当店スタッフが親身に回答しています。
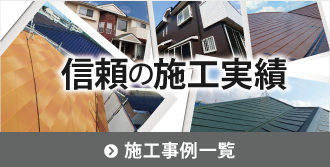
弊社で行った施工事例をご紹介しています。詳細な説明と写真でわかりやすくお伝えします。
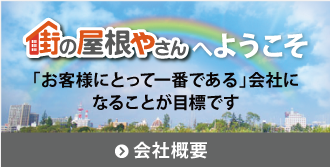
弊社の会社概要になります。街の屋根やさんとはこんな会社です。






