ホーム > 新居浜市の雨漏り修理施工事例。穴の開いた銅板を交換し雨漏り解…

新居浜市の雨漏り修理施工事例。穴の開いた銅板を交換し雨漏り解消。他屋根全体の漆喰や瓦のズレをメンテナンス。
新居浜市 屋根材(瓦)
【工事のきっかけ】
「納戸のからの雨漏りを直してほしい。」との依頼を受け現場へ伺いました。
納戸部分は家の西側でその部分だけ壁が突出している形だったので、大屋根の下に切妻屋根を作っている形でした。
大屋根から流れた雨が納戸部分の屋根に流れる時、板金で受けて両サイドに流すのですが、その板金が雨を受ける部分で
裂傷が見られ、雨漏りの原因でした。
棟を壊して、谷部分の板金を交換する修理が必要です。
その他屋根全体を確認し、谷部分で加工した瓦のズレや隅棟の漆喰の劣化も説明し、その部分のメンテナンスを含めた修理を実施させて
いただきました。
基本情報
- 使用材料:シルガード白(漆喰) コーキング ガルバリウム鋼板(カラーステン)

みなさんこんにちは。
街の屋根やさん新居浜中央店の合田です。
本日は雨漏りの無料点検に向かいました。大雨の時に納戸の部屋から雨漏りがするそうです。
点検は無料になっております。

雨漏り箇所は納戸の部屋らしいです。(写真が無いです。すいません。)
とにかく雨漏り箇所の真上の屋根を見てみましょう。
何やら瓦と接合している銅板が怪しいです。

大屋根の瓦を除けてみました。
納戸の部屋だけ壁部分が突出していて、屋根も一段低い形状です。
取り合い部分は樋が付けれないので谷板金で雨水を受けて左右に流すようにしています。
瓦と当たっていた部分に亀裂がありました。
ちょうど、大屋根の雨水が流れ落ちるところです。
銅板は初めはピカピカしていますが古くなってくると緑色になってきます。
古い10円玉が錆びてくると緑色になるのと同じ原理です。
空気中の酸素に触れて反応するので避けられない現象です。
そこから劣化が進み穴が空いてしまいます。
1度コーキングをしていましたが古く硬化したのと
穴が広がり、また入ってきたのでしょう。
原因はここですね。

応急的にコーキングを新しく付け直しておきました。
ただし交換しておいた方が良いでしょう。
雨漏り箇所以外にも屋根を点検します。
屋根上は危険ですから、専門業者さんに見てもらうタイミングで全体的に
確認してほしい要望もあります。
1つ目は谷の瓦です。
加工部分が何枚か落ちています。
谷の板金が下にあるので釘固定で出来ない部分です。
銅線で瓦を連結したり、釘穴から銅線で引っ張って屋根板に打ち付けたり
することが多いです。
この部分の瓦みたいにズレると瓦と板金の重なりが少なくなり、大雨とかで
水の量や流れる速さが上がれば板金を越えて雨漏りの恐れが出てきます。
(オーバーフロー)

棟違い(同一屋根で棟の位置が途中で異なること)の漆喰にも
モルタルが古くなって亀裂が走っています。
雨がモルタルに直接当たると、亀裂から浸み込んできます。

葺止(壁際)の瓦も漆喰で止めていましたが経年で剥離しています。
結構分かりにくいのですが
谷部分が軒先まで行かず、途中で終わっている場所は
右写真のように潜り込みがあります。
屋根面と屋根面が交わる部分なので瓦も加工して取り付ける部分が多いです。
ここの潜り込み部分、瓦を加工しすぎて屋根面が見えています。
瓦の形状上雨が吹き込むと加工部分に流れてしまいます。

後は瓦破損が2枚ほどありました。

以上で点検が終わりました。
メインの板金部分は棟を壊すため少し時間がかかります。
漆喰塗部分などは量が少なかったので日数による費用は増え無さそうな感じでした。
上記の説明をしたところ、説明した箇所の修繕も合わせて実施させていただくことになりました。
ありがとうございます。

棟や谷部分修理では御なじみの棟取り除けです。
棟の中に雨が侵入していれば土はベショベショ状態です。
湿り乾きを繰り返したり、年数が経ってくると土はパサパサになります。
パサパサ状態になると瓦との密着が無くなり棟が崩れやすくなる恐れがあります。
劣化した板金部分を除けると奥が確認できます。
ちょうど壁際に捨て水切が付いています。
捨て水切は防水シートと瓦の間に付ける板金です。
風が強い横降りの雨で瓦の隙間に吹き込んだり、壁に伝った雨水が侵入しようとしても
この水切が受けて樋まで流れるようになります。
この水切は特に問題ないようです。

破損していた銅板金の下です。
雨が落ちて土が一部流れてくぼみができています。

棟際の瓦を除けると、土に混じった雨水が流れている跡が
分かりました。

棟を復旧していきます。
今は土ではなくシルガード(漆喰)を使います。
固まると水を弾く効果があるので防水性能は抜群です。
板金を加工して谷部分を作成します。
通常の谷部分とは異なるのでイチから作成します。
のし瓦系統は初めに片紐大面を積んでいきます。
のし瓦には
・大面瓦
・のし瓦
・反り、削ぎ瓦などがあります。
紐付きとは写真の赤丸部分の突起があるものを言います。
紐部分で外側の継ぎ目が重なるので仕上りが綺麗に見えます。
どの、のし系統をいくつ使うかは
鬼瓦の形や大きさによってどの瓦を使用するかが変わってきます。
のし瓦、紐のし瓦を積んでいきます。
もちろん修理の場合は元の位置で復旧していきます。
のし瓦と大面瓦の大きな違いは
写真の赤丸部分の垂(タレ)の有無ですね。
大面瓦は幅が広く垂があるのが特徴です。
棟で積むのし瓦の1番下に使用します。
垂部分は棟から段々と流れる雨を棟の内側に入れずに水を切るためです。
脚の長い鬼瓦によく使われます。
ハコのし瓦と言うこともあります。
のし瓦は幅が大面瓦に比べれば狭いです。
垂は無くなめらかです。
小さめの鬼瓦の場合は1番下から使用する場合もあります。
基本的に2段目からは、のし瓦を使用します。
上段の丸棟を取り付けて復旧完了です。
谷側はもちろん雨水が入らないよう漆喰とコーキングで覆います。
以上で雨漏り箇所の修理が終わりました。

調査したときに谷部分の瓦がズレていました。
谷の板金と瓦が重なる部分はこうなる状態が良く見られます。
板金上に釘固定が出来ないので、コーキング(接着剤)や
釘穴から銅線を引っ張って釘固定する場合があります。
瓦そのものを固定出来ないので時間が経つとガタついてきます。

瓦は上下左右どこかは隣の瓦と重なる部分があります。
重なる2枚をドリルで穴を開けて括りつけて固定します。
棟や壁際など土を使用する部分は表面にモルタルをして
雨漏りを塞いでいます。
しかし表面のモルタルは時間が経って古くなると
亀裂が入って割れたり、剥離したりします。
そこから隙間が生じると雨漏りのリスクが高まります。
古くなったモルタルは全て取り除けます。
古いモルタルの上に塗っても土との接着は古いままなので効力がありません。
また、日差しや雨や風の当たる場所とそうでない場所では劣化の進行が
大きく異なりますが、1度に全て塗り直す方がおススメです。

土にモルタル強固液を塗ります。
土と漆喰との接着を強めます。
意外と漆喰はたくさん塗っています。
屋根の形が複雑になるほど塗っている場所は増えます。
剥離している葺止(壁際)の瓦も隙間に雨水が入る可能性があるので
補修します。
壁際と言うよりは破風板ですね。
切妻形状の両端部分の板です。
1度瓦を除けます。
袖瓦から垂れる雨水も中に入るので注意です。
パイプも伸びているので厄介です。

シルガードとコーキングで隙間を塞ぎます。
ちゃんと瓦上に流れるようにシルガード、コーキングにも
傾斜をつけておきます。

ここは谷板金下の潜り込み部分です。
点検時のブログでも言ったとおり、吹き込むと瓦下に雨水が落ちるリスクが高いです。
瓦の流れに沿って漆喰を詰め雨水の吹き込みを遮断します。
正面も漆喰を詰めます。吹き込みを正面、側面から遮断しているので大丈夫です。
正面だけだとダムを作るようなものなのでこのやり方はしてはいけません。
以上でメンテナンス終了です。
写真忘れて申し訳ありませんが破損瓦も交換しております!!
雨漏りなど直面するトラブルもあれば、屋根に上がらないと分からないトラブルもあります。
新居浜市で雨漏りにお困りの方、屋根点検をしてほしい方はお気軽にご連絡ください。
屋根で困ったこと、相談したいことがあれば
街の屋根やさん新居浜中央店にお気軽にご相談ください。
・新居浜市(新居浜、別子山)
・西条市(西条市、小松町、東予市、丹原町)
・四国中央市(土居町、三島、川之江、新宮村)で主に活動中
その他愛媛県内の地域のみなさまも是非!
0120-32-6886
ご相談、点検、御見積は無料です。
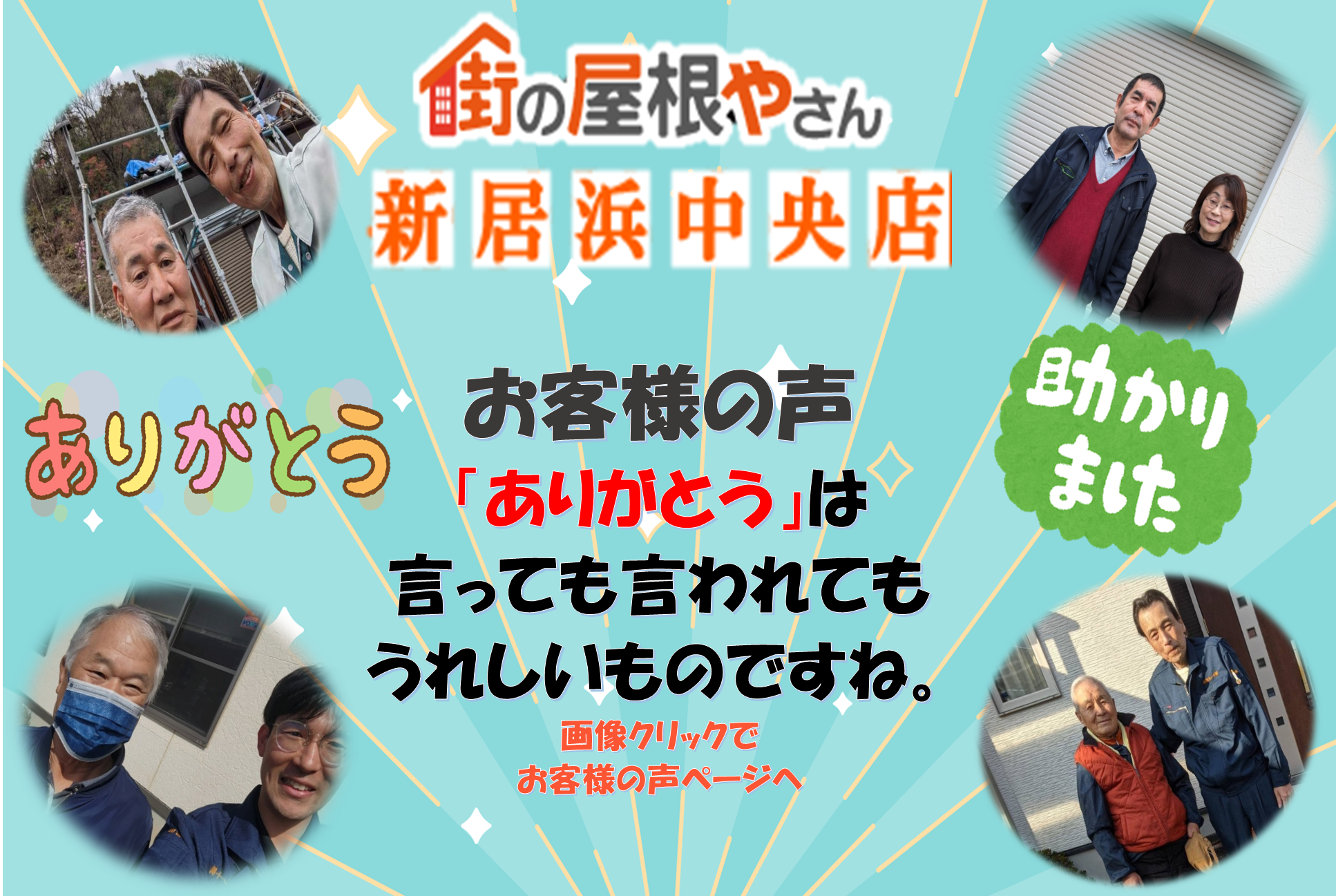
お客様の声一覧はこちらからです。
屋根のお悩み、当社の対応など当社で施工、修理していただいた方に
アンケート、写真としてご協力いただいております。
快い対応、本当に感謝しております。
この記事を書いた加盟店

電話 0120-989-742
E-Mail machiyane-niihama@higaki-roofest.com
桧垣スレート株式会社
〒792-0811
愛媛県新居浜市庄内町3丁目1−46
愛媛県の加盟店一覧

電話 0120-989-742
E-Mail machiyane-ehime@tankawara.co.jp
有限会社丹瓦建材店
〒793-0073
愛媛県西条市氷見丙466

電話 0120-989-742
E-Mail machiyane-ehime@tankawara.co.jp
有限会社丹瓦建材店
〒791-1102
愛媛県松山市来住町798−7
ベルメゾン南久米102号室

共通の施工事例はこちら
記事がありません
表示する記事はありませんでした。
各種屋根工事メニュー
私たち『街の屋根やさん』は神奈川県を含む関東全域を施工エリアとする、お住まいの屋根の専門店です!
街の屋根やさんでは下記の工事を取り扱っております。工事内容の詳細は各工事ページでご確認下さい。

街の屋根やさんが施工している様々な屋根工事と屋根リフォームの一覧をご紹介します。

お客様の不安を解消できるように、お問い合わせから工事の完成までの流れをご紹介しています。

街の屋根やさんが施工している様々な屋根工事と屋根リフォームの一覧をご紹介します。
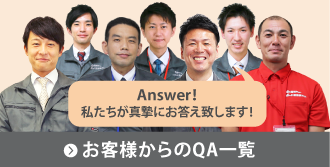
お客様から寄せられた屋根に関する疑問を、当店スタッフが親身に回答しています。
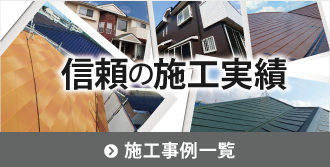
弊社で行った施工事例をご紹介しています。詳細な説明と写真でわかりやすくお伝えします。
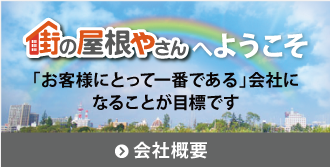
弊社の会社概要になります。街の屋根やさんとはこんな会社です。






